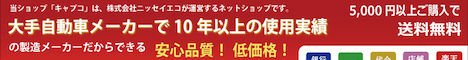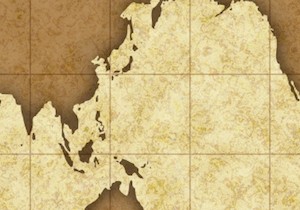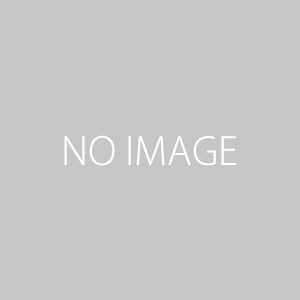AIリテラシー
動画生成AIモデルの「SORA」が「SORA2」にアップグレードしたようです。最近では、全編AIで作られた映画もあるそうです。
そういえば最近、YouTubeでは現実では信じがたい映像がショート動画で流れてくるのですが、ぱっと見たところでは実際の映像と思えるほど精巧で、「そんなことはない」と疑いをもって注視してみないと、AIで生成された動画だと分からないほどの完成度でした。そこには「SORA」の透かしが入っていました。
ここまでくると、現実と勘違いする人が多数出るでしょうし、すでに政治や時事問題を利用したフェイク動画が社会問題にも発展しています。いずれ、流れてくる動画が現実なのかAIなのか、人の目では判断できないほどの精度になり、フェイクを検知するのもAIが行うようになるのでしょうか。ウイルスとウイルス対策ソフトのような、いたちごっこがAIの世界でも起きてくるのかもしれません。
さぁどうしたらAIに騙されないのでしょうか?Chat GPTに聞いてみました。
1. 動画の「出どころ」を確認する
- 公式発信か?
→ 政府機関・企業・ニュースメディアなどの公式SNSや公式サイトから出ているかを必ずチェック。 - 拡散元が不明な動画は要注意。
→ 匿名アカウントや再投稿、切り抜きはフェイクの温床です。
2. 内容が「感情を強く揺さぶる」ものは一呼吸おく
AIフェイクは、怒り・恐怖・感動など強い感情を刺激する内容で広まりやすく作られています。
→「本当かな?」と思って冷静に調べるクセをつけましょう。
3. 映像や音声に不自然な点がないか観察する
以下のような特徴があればフェイクの可能性が高いです。
- 口の動きと声が微妙にずれている
- 瞬きや表情が不自然
- 髪や背景がぼやけている
- 照明・影の方向が不自然
- 音声の抑揚が一定すぎる
4.信頼できるニュースやファクトチェックサイトを確認
代表的なサイト:
- AFP通信「AFP Fact Check」
- 日本ファクトチェックセンター(JFC)
- Snopes(英語)
5. 技術的検知も進化中(知っておくと安心)
- 一部SNS(例:YouTube、X、Metaなど)はAI生成コンテンツに「ラベル」表示を始めています。
- AI生成動画には**メタデータ(透かし)**が埋め込まれる場合も。
→ 今後、一般ユーザーも判別しやすくなっていきます。
まとめ:騙されない5か条
- 出どころを確認する
- 感情的にならない
- 不自然な映像・音に注意
- ファクトチェックを活用
- 共有前に一呼吸おく
AIのことはAIに聞くのが一番――なんだかそんな時代になってきましたね。気づけば、生活の中でも仕事の中でも、AIはすっかり欠かせない存在になっています。
でも、AIを上手に使いこなすためには、AIの得意なこと・苦手なことを知っておくことが大切です。さらに、倫理的な問題や社会への影響についても理解したうえで、日常や仕事に活かしていく力――それが「AIリテラシー」です。
ITリテラシーの次はAIリテラシー。
デジタル技術の進化には終わりがなく、これからも私たちの暮らしをどんどん変えていくのでしょう。