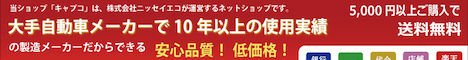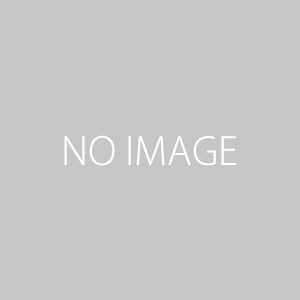大きな声で
先日、いきいきプラザでの月次祭で、祭主を務めていただいた先生から祭典後の講話でこのような話をいただきました。
天理教の月次祭では、「おつとめ」と呼ばれる歌と踊り(手踊り)に合わせて、鳴物と呼ばれる和楽器(拍子木、チャンポン、太鼓など)を奏でますが、その和楽器を奏でる際に「何が一番大切ですか?」 という問いが出されました。
1.音の大きさ
2.他の楽器と音色(メロディー)を合わせること
3. 他の楽器とテンポ(速さ)を合わせること
参加した私たちの大半の回答は、「3.他の楽器(人)とテンポを合わせること」でした。 テンポ(速度)が合わせること「ハーモニー」が合わないと弾いてる人も聞いている人もバラバラになってしまうから。 毎月指導を受けている雅楽の先生からも、篳篥、龍笛、笙の他の人の音を聞いてスピードを合わせること、とよく注意を受けますし、3管が合わないと、必ず基礎となる唱歌に戻って練習させられます。
しかし、この先生の答えは、「1.音の大きさ」が一番大切です!!
理由は、楽器を吹く上で、自分で意識しないと大きな音は出せないから。 例えば、気持ちが落ち込んでいる時や、嫌なことがあった時、悩みがある時など、前向きな気持ちでない時はどうしても声が小さくなってしまいます。 声の大きさや音の大きさは、やはり「元気」の表れであり、自分の心が勇んで前のめりになってないと、大きな音は奏でられないという理由でした。
一度、奏でる音を小さくしてしまったら、なかなか大きな音に戻すことができない。 だから常に大きな音を意識して吹き続けなければならないと。
「なるほど!」確かに、常にやる気がある状態を保つのは難しいが、それを常に実行できる人にならなければならないと。
当社の社是に「一に勢い」がありますが、この勢いとは、皆が勇んでいること、皆が元気いっぱいであること、大きな声で挨拶をすること、社員一人一人の活気を見て、この会社は勢いがあると、周囲の会社さんや来社したお客様を感じさせることができます。
その為、大きな声というのが、「勢い」の基本ではないかと感じました。
私たちの日常、仕事が忙しい時もありますし、自分の思い通りにならない時、仕事以外でもプライベートでの悩みや家族の問題など、誰でも気持ちが冴えない時は必ずあります。 それでも、会社に出社したら「一に勢い」を意識して大きな声を出すこと、話すトーンを上げることにより、周りの人たちに元気を与えて、自然と自分も元気を取り戻せるきっかけになると思います。
体調が優れない時は? 「病は気から」という言葉もありますので、出来る範囲で良いので実践してみて欲しいです。